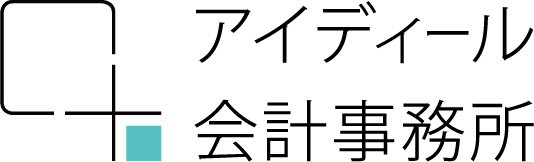従業員の福利厚生の一環として、従業員に食事を支給している企業やこれから支給しようとしている企業も多いのではないでしょうか?
それでは、従業員へ食事を支給する際の税務上の注意点やポイントを解説していきます。
まず食事代は本来、従業員個人が負担するものであるという点です。
そうすると、食事代を負担してもらった従業員としては「食事代を負担する必要がなくなった」という恩恵を受けていることになります。
こういった現金などの金銭以外で恩恵を受けたものを、税法用語では『経済的利益』といいます。
従業員が会社から『経済的利益』を受けている場合は、『給与』とみなされる可能性があり所得税・住民税が課税されることがありますので注意してください。
ただし食事代の場合は、『経済的利益』を受けていたとしても要件を満たしていれば給与として課税されることはありません。
課税されないための要件や、実際の取り扱いがどのようになっているかを見ていきましょう。
国税庁のHPにあるタックスアンサー(よくある質問)に回答が掲載されています。
下記国税庁ホームページより抜粋。一部解説を加筆。
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額(食事代のうち会社に負担してもらった金額)が1か月当たり3,500円(税抜)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
(例)1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合
この場合には、上記(1)の条件を満たしていません。➡従業員が半分負担していないので要件を満たさない。
したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
(1)仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
(2)社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。➡残業時の食事代を現金支給する場合は300円以下。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
となっております。
また食事代全てに上記の要件が適用されるわけではなく、会議を伴っている場合や下記のような場合は、会議費又は福利厚生費として良いとされています。
創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用。➡イベント時の食事代で贅沢過ぎないもの。
ポイントをまとめると、
従業員への食事代を給料課税されないためには?
(1)従業員が食事代の半分以上を負担しており、「食事代」と「従業員の負担」の差額が、1ヵ月あたり3,500円(税抜)以下であること。
➡つまり従業員が恩恵を受けた金額が、1ヵ月あたり3,500円以下で半額は自己負担していること。
(2)残業又は宿直を行う時に支給する食事代であること。
(3)イベント時などに従業員に、概ね一律に支給する食事代であること。
給与とみなされてしまうと、どうなってしまうの?
・従業員個人に『所得税・住民税』がかかってしまい、過去に遡って納税をする必要があります。
・消費税が本則課税の場合は、食事代を支払った時の消費税について仕入れ税額控除が受けられなくなる可能性があり過去に遡って納税をする必要があります。
対策としては、どうすればいい?
・従業員に食事代を半額負担してもらう。かつ、会社負担額1カ月3,500円以下である。
➡従業員の負担を抑えたい場合は、負担相当額の給料を増額する。
・食事を支給するのは、残業や宿直がある時のみにする。
ちなみにうちの事務所の場合は・・・、
職員の外出が多く、社内にいる人のみに食事を支給すると不公平感が出てしまうため、食事の支給は基本的には行ってません。
特例としては、
・月初は会議を兼ねて食事(会社負担)
・繁忙期明けや忘年会などの打ち上げ的な食事(会社負担)
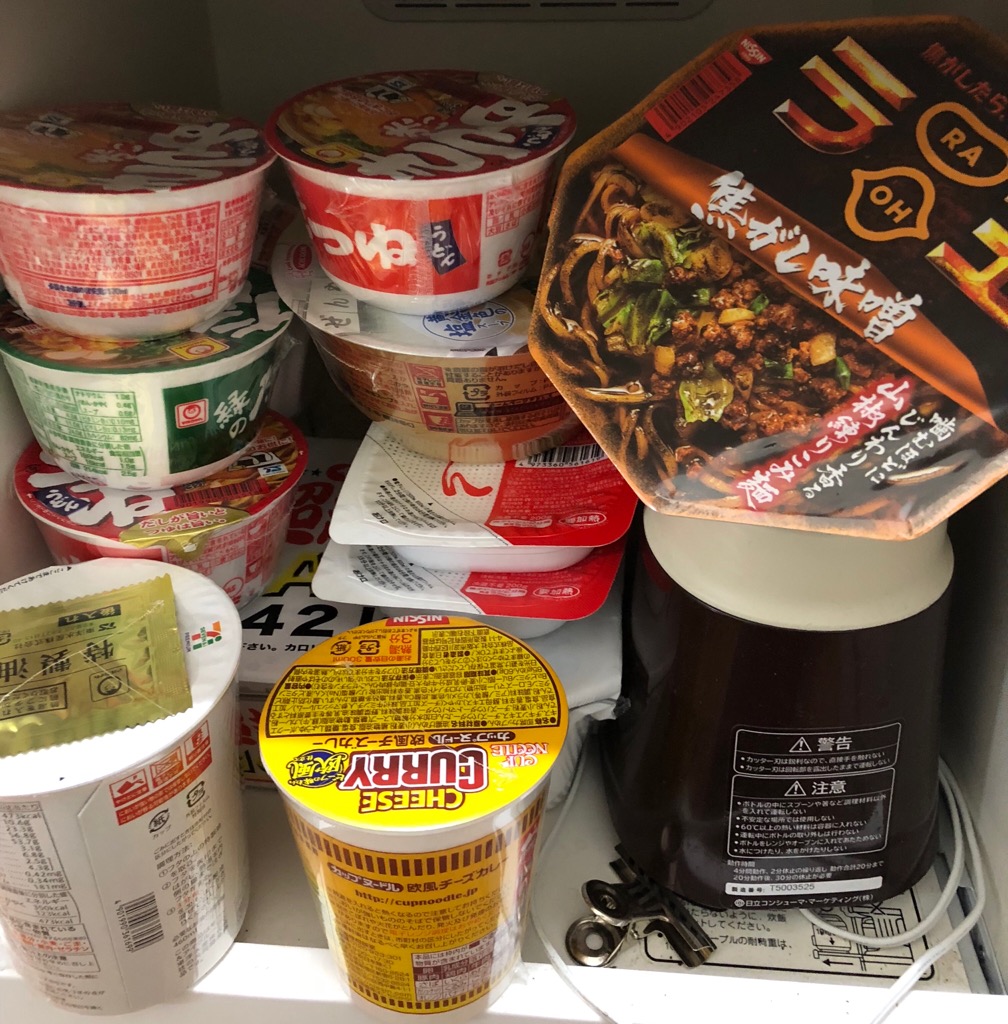
ちなみに、カップラーメンは食べ放題です(笑)
といっても残業時の非常食になっているので、要件は満たしていますね!
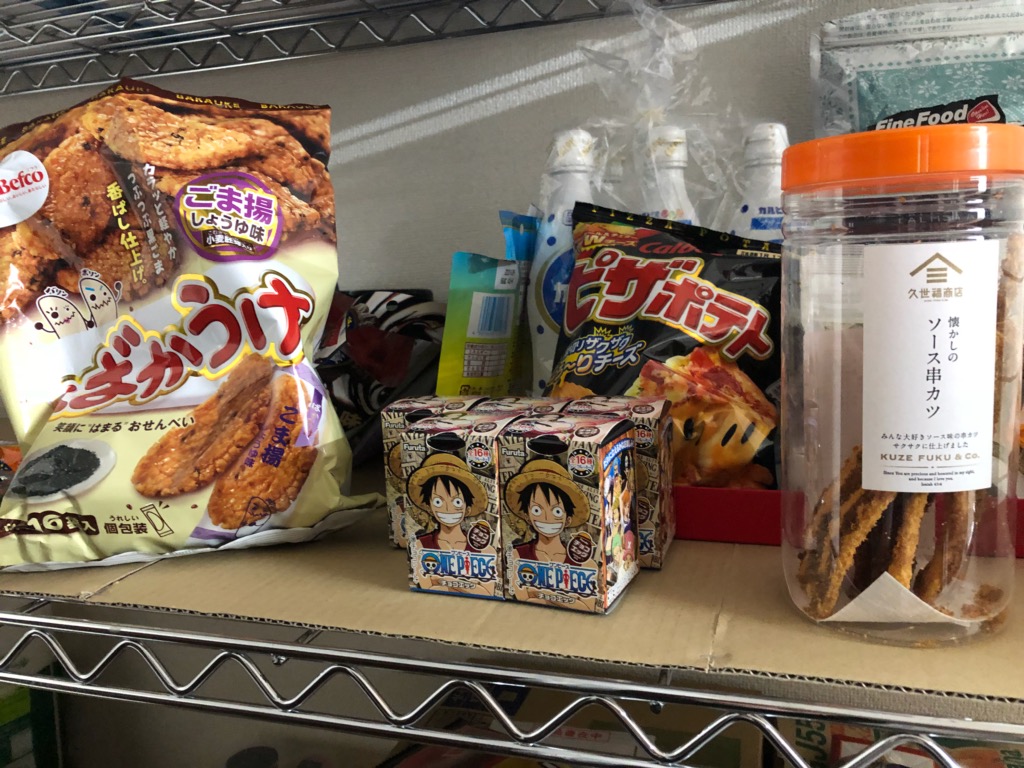
お菓子も食べ放題です。

コーヒーやカフェラテも飲み放題です。
働きやすい環境を作りたいとう想いは、この記事を読んでいる経営者の方と同じです!
本来、福利厚生の充実や従業員満足度を上げるために行った取り組みのせいで、後にトラブルにならないように注意したいところですね。
具体的な対策や個別の事案につきましては、ご相談下さい。